
【最新公開シネマ批評】
映画ライター斎藤香が現在公開中の映画のなかから、オススメ作品をひとつ厳選して、ネタバレありの本音レビューをします。
今回ピックアップするのは英国の名匠ケン・ローチ監督作『家族を想うとき』(2019年12月13日公開)です。是枝裕和監督が大尊敬する映画監督であるケン・ローチの作品は、社会の弱者にスポットをあてた作品が多く、リアリティある人物描写でさまざまな家族の姿を見せてくれます。本作は英国の労働者階級の家族の今を切り取った作品で、すご~く考えさせられます。では物語から。
【物語】
マイホーム購入を夢見ているリッキー(クリス・ヒッチェン)とその家族。しかし、リッキーは住宅金融組合の破綻により、住宅ローンを組めなくなったばかりか、建設の仕事も失ってしまいます。「なんとか家族にマイホームを!」と、彼が見つけた新たな仕事は宅配ドライバー。個人事業主なので頑張れば頑張るだけ稼げる!一抹の不安を抱えながらも、介護職の妻のアビー(デビー・ハニーウッド)が使っていた車を資金に、宅配に使うトラックを購入。しかし、バスで介護先へ向かうようになったアビーは子供二人と過ごす時間が少なくなり、16歳の長男は問題行動を起こすように……。
【ささやかな幸福を奪う負の連鎖】
大変見ごたえのある映画でした。個人事業主として働き始めた主人公が、過酷な職場で搾取されていき、家族のために頑張っているのに、家族が崩壊していく……。なにせリッキーは週6日、1日14時間労働。子供のトラブルで休みをもらおうとすると、上司は「代わりのドライバーが見つからなかったら、1日100ポンド(約1万4千円)の罰金な」なんていうんですよ! でもみんなスケジュールぎちぎちで働いているから代わりなんて見つからない。ネットショッピングが増えて配達する荷物が山積みの中、会社側も休まれては困るのかもしれないけど、あまりにも一方的で高圧的な態度には、本当に腹が立ちました。
一方、訪問介護の仕事につく妻のアビーは「介護先の人は、自分の母親だと思って世話をするの」という優しい女性です。しかし、車を売ってしまったのでバス移動。遠い場所で連日ハードな仕事が続き、疲れ果てています。家族団らんの時間はなく、生活を立て直せる気配もない。そんな彼らを観て「こんなに頑張っているのになんで!」と心の中で叫びましたよ。
【家族は人生の土台】
両親が忙しすぎて、帰宅しても疲れ果てていると、やはり思春期の子供たちの心はざわつくんですね。特に長男は不満のはけ口を外に見出してトラブルを起こし、私は「両親が頑張っているのに、警察のお世話になるようなことして、何やってるのよっ!」と近所のおばちゃん気分で怒りがわきましたが、息子はまだ両親の仕事の事情がわからない。「あんなに忙しいのに、なんで家は貧しいんだ。なんで家に帰って来ないんだ」と思い、苛立っているんですね。長女が比較的冷静に状況を見つめ、家族を助けようとしているのが救いです。
家族がうまく機能していないと、人間ってささくれだって弱っていくものなのですね。やはり人生の土台は家族にあるのかなと改めて思いました。
【英国だけじゃない、日本でも起こっていること】
個人事業主という仕事の形態が悪いわけではなく、やはり雇う側が儲け主義に走りすぎているのが問題ではないかと私は感じました。リッキーの家族だって、狭いながらも賃貸の住む家があり、贅沢しなければ生きていけるけど、その生活を維持することに精いっぱいで、ものすごく働いているのに、それより多くは望めないんです。それは彼らの頑張りが足りないからでしょうか?
ケン・ローチ監督の映画は、声高に力強いメッセージを提示することはありませんし、英国の社会問題を具体的に言及することもしません。ただ、リッキーとその家族に起る出来事をまっすぐに見つめて映し出しているだけ。でもそれだけでわかるんです。英国の市井の人々の厳しい現実と社会の問題点は、日本が抱えている問題と一緒だということが。
家族を通して社会を映し出すスタンスはローチ監督と是枝監督は確かに似ているけど、本作は是枝作品よりもリアルでハードに映るかもしれません。でも考えるべき問題が描かれています。働く女性たちにぜひ見てほしい力作です。
執筆:斎藤香 (c)Pouch
『家族を想うとき』
(2019年12月13日より、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国ロードショー)
監督:ケン・ローチ
出演:クリス・ヒッチェン、デビー・ハニーウッド、リス・ストーン、ケイティ・プロクター、ロス・ブリュースター
photo: Joss Barratt, Sixteen Films 2019
© Sixteen SWMY Limited, Why Not Productions, Les Films du Fleuve, British Broadcasting Corporation, France 2 Cinéma and The British Film Institute 2019







 カンヌ最高賞受賞!韓国映画『パラサイト 半地下の家族』はコメディから予測不能サスペンスへと展開していく名作です
カンヌ最高賞受賞!韓国映画『パラサイト 半地下の家族』はコメディから予測不能サスペンスへと展開していく名作です 【カンヌ最高賞】映画『万引き家族』は自分の中の “正義” が揺さぶられる傑作 / 社会に見捨てられた家族の生き様に胸がエグられます【最新シネマ批評】
【カンヌ最高賞】映画『万引き家族』は自分の中の “正義” が揺さぶられる傑作 / 社会に見捨てられた家族の生き様に胸がエグられます【最新シネマ批評】 阿部寛のダメ男っぷりに苦笑…是枝監督の新作『海よりもまだ深く』は家族あるあるに大共感の団地映画【最新シネマ批評】
阿部寛のダメ男っぷりに苦笑…是枝監督の新作『海よりもまだ深く』は家族あるあるに大共感の団地映画【最新シネマ批評】 【映画批評】是枝監督最新作『ベイビー・ブローカー』! 赤ちゃんの母・ソヨンの変化に釘付けになりました
【映画批評】是枝監督最新作『ベイビー・ブローカー』! 赤ちゃんの母・ソヨンの変化に釘付けになりました 2017年何かいいことが起こりそう!と思わせてくれる映画4選☆ 家から出ずにパッと観られるAmazonビデオからピックアップ
2017年何かいいことが起こりそう!と思わせてくれる映画4選☆ 家から出ずにパッと観られるAmazonビデオからピックアップ 【夜の4コマ部屋】バレませんように② / サチコと神ねこ様 第2170回 / wako先生
【夜の4コマ部屋】バレませんように② / サチコと神ねこ様 第2170回 / wako先生 台湾の定番レストラン「鼎泰豊(ディンタイフォン)」はおひとり様でもOK?1人で注文するときのコツも紹介
台湾の定番レストラン「鼎泰豊(ディンタイフォン)」はおひとり様でもOK?1人で注文するときのコツも紹介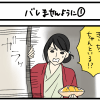 【夜の4コマ部屋】バレませんように① / サチコと神ねこ様 第2169回 / wako先生
【夜の4コマ部屋】バレませんように① / サチコと神ねこ様 第2169回 / wako先生 靴と生きる人生の救世主👟上履きの手洗いがメンドクサイから洗濯機にポイするだけの「靴用洗濯ネット」を使ってみた
靴と生きる人生の救世主👟上履きの手洗いがメンドクサイから洗濯機にポイするだけの「靴用洗濯ネット」を使ってみた デカいパフェの上に鎮座するデカい大福!卵型のかき氷でおなじみのTAMAGOYAから「お抹茶デラックスパフェ」が登場
デカいパフェの上に鎮座するデカい大福!卵型のかき氷でおなじみのTAMAGOYAから「お抹茶デラックスパフェ」が登場 【夜の4コマ部屋】コンコントーク⑩ / サチコと神ねこ様 第2167回 / wako先生
【夜の4コマ部屋】コンコントーク⑩ / サチコと神ねこ様 第2167回 / wako先生 【夜の4コマ部屋】コンコントーク⑨ / サチコと神ねこ様 第2166回 / wako先生
【夜の4コマ部屋】コンコントーク⑨ / サチコと神ねこ様 第2166回 / wako先生 【夜の4コマ部屋】コンコントーク⑪ / サチコと神ねこ様 第2168回 / wako先生
【夜の4コマ部屋】コンコントーク⑪ / サチコと神ねこ様 第2168回 / wako先生 【夜の4コマ部屋】コンコントーク⑧ / サチコと神ねこ様 第2165回 / wako先生
【夜の4コマ部屋】コンコントーク⑧ / サチコと神ねこ様 第2165回 / wako先生 【夜の4コマ部屋 プレイバック】お花見 / サチコと神ねこ様 / wako先生
【夜の4コマ部屋 プレイバック】お花見 / サチコと神ねこ様 / wako先生 【夜の4コマ部屋】コンコントーク⑥ / サチコと神ねこ様 第2163回 / wako先生
【夜の4コマ部屋】コンコントーク⑥ / サチコと神ねこ様 第2163回 / wako先生 【夜の4コマ部屋】コンコンリゾート③ / サチコと神ねこ様 第2151回 / wako先生
【夜の4コマ部屋】コンコンリゾート③ / サチコと神ねこ様 第2151回 / wako先生 【夜の4コマ部屋】コンコンリゾート⑧ / サチコと神ねこ様 第2156回 / wako先生
【夜の4コマ部屋】コンコンリゾート⑧ / サチコと神ねこ様 第2156回 / wako先生 【夜の4コマ部屋】コンコントーク④ / サチコと神ねこ様 第2161回 / wako先生
【夜の4コマ部屋】コンコントーク④ / サチコと神ねこ様 第2161回 / wako先生 濡れたハンカチをバッグにしまうってなんか嫌→無印良品「99円で解決できますよ」
濡れたハンカチをバッグにしまうってなんか嫌→無印良品「99円で解決できますよ」 【2024年福袋情報まとめ②】よなよなエールや無印良品が登場!やっぱり人気の福袋はもちろん初めて福袋を販売するブランドもあるよ
【2024年福袋情報まとめ②】よなよなエールや無印良品が登場!やっぱり人気の福袋はもちろん初めて福袋を販売するブランドもあるよ 漫画『ゴールデンカムイ』が実写映画化! 14名のキャストが解禁もSNSではなぜか「あの人」がトレンド入りしてました
漫画『ゴールデンカムイ』が実写映画化! 14名のキャストが解禁もSNSではなぜか「あの人」がトレンド入りしてました 【レポ】ミスドの食べ放題「ドーナツビュッフェ」に挑戦🍩元は取れる?お得に楽しむコツはある?
【レポ】ミスドの食べ放題「ドーナツビュッフェ」に挑戦🍩元は取れる?お得に楽しむコツはある? バレンタインで余ったチョコを安く買える! フードロスを解決する「もうひとつのバレンタイン」
バレンタインで余ったチョコを安く買える! フードロスを解決する「もうひとつのバレンタイン」 映画ライターが選ぶ絶対に見て欲しい「2018年上半期の映画ベスト5」を発表! ディズニー映画「リメンバー・ミー」やカンヌ最高賞を受賞した「万引き家族」など
映画ライターが選ぶ絶対に見て欲しい「2018年上半期の映画ベスト5」を発表! ディズニー映画「リメンバー・ミー」やカンヌ最高賞を受賞した「万引き家族」など 手話のセリフと歌であふれる感情を表現! 19歳の新人女優が話題のフランス映画『エール!』エリック・ラルティゴ監督に直撃インタビュー
手話のセリフと歌であふれる感情を表現! 19歳の新人女優が話題のフランス映画『エール!』エリック・ラルティゴ監督に直撃インタビュー アカデミー賞作品賞候補作『アメリカン・スナイパー』で体感する戦争と死の恐怖!【最新シネマ批評】
アカデミー賞作品賞候補作『アメリカン・スナイパー』で体感する戦争と死の恐怖!【最新シネマ批評】 福山雅治×是枝裕和監督の新作『三度目の殺人』は法廷を舞台にした社会的弱者の復讐劇【最新シネマ批評】
福山雅治×是枝裕和監督の新作『三度目の殺人』は法廷を舞台にした社会的弱者の復讐劇【最新シネマ批評】 【本音レビュー】もっとユーモアがほしかった! 話題作『未来のミライ』は現実感たっぷりの家族映画でした
【本音レビュー】もっとユーモアがほしかった! 話題作『未来のミライ』は現実感たっぷりの家族映画でした 【2018年】オススメ映画ベスト5を映画ライターが厳選してご紹介! 「プーと大人になった僕」「万引き家族」など
【2018年】オススメ映画ベスト5を映画ライターが厳選してご紹介! 「プーと大人になった僕」「万引き家族」など 法廷ドラマ『ジャッジ 裁かれる判事』の頑固な父と息子の濃い~確執は、意外と女子必見!【最新シネマ批評】
法廷ドラマ『ジャッジ 裁かれる判事』の頑固な父と息子の濃い~確執は、意外と女子必見!【最新シネマ批評】 仕事に子育て、介護に不倫…レア・セドゥが30代女性の等身大の姿を熱演! 映画『それでも私は生きていく』はじっくり鑑賞したい
仕事に子育て、介護に不倫…レア・セドゥが30代女性の等身大の姿を熱演! 映画『それでも私は生きていく』はじっくり鑑賞したい 【本音レビュー】樹木希林の遺作『命みじかし、恋せよ乙女』で見せるラスト15分の名演は圧巻! しかし賛否両論映画でもあるのです…
【本音レビュー】樹木希林の遺作『命みじかし、恋せよ乙女』で見せるラスト15分の名演は圧巻! しかし賛否両論映画でもあるのです… 【映画レビュー】マーベル新作『ブラック・ウィドウ』は最高なアクション&愛情深さを堪能できる傑作! 妹エレーナにも注目です
【映画レビュー】マーベル新作『ブラック・ウィドウ』は最高なアクション&愛情深さを堪能できる傑作! 妹エレーナにも注目です 是枝監督の新作『ベイビー・ブローカー』は初の韓国映画! パラサイトやイカゲームのキャスト&スタッフが大集結しているんです
是枝監督の新作『ベイビー・ブローカー』は初の韓国映画! パラサイトやイカゲームのキャスト&スタッフが大集結しているんです
コメントをどうぞ